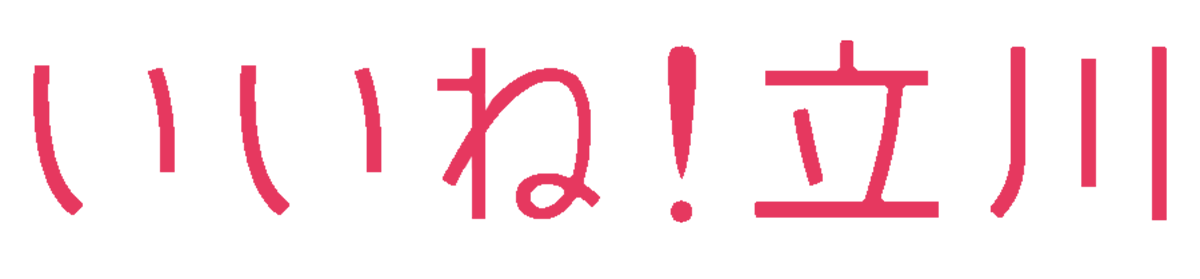『いいね!立川』では記事タイトルや本文に「らしい」「みたい」といった表現をたくさん使っています。
ライター経験(とくに紙媒体)のある方や、正確な情報を求める方からすると、モヤッとするポイントなんじゃないでしょうか。
今回は、なぜいーたちが「らしい」「みたい」を多用するのかを解説したいと思います。
いーたちには「ウソを書かない」というルールがある
『いいね!立川』の記事では「ウソを書かない」ということを大事にしています(誤植は除きます、ゴメンナサイ)。
そのため、基本的には取材先のお店や会社に対してはアポを取らず、外から見える範囲、一般市民として見聞きできる範囲の情報に基づいて記事づくりをしています。
たまに読者さんからコメント頂くのが「ちゃんと取材して正確な情報を載せなさい」というもの。
でもここでちょっと待ってほしい!
果たしてちゃんとアポをとって取材した記事は、正確な情報が載っているのでしょうか?
私たちメディアが名乗った上でアポを取って取材をすると、取材される側はほとんどの方が「取材受けモード」で言葉を紡ぎます。商品も特別仕様になったりする。
これってウソにつながるよね、と私たちはそう考えています。
また、取材時は正しい情報であったとしても、読者さんが読む頃にはもう内容が変わってしまっていることも多いです。
宇宙のすべては常に変わっています。だから言い切って書いてしまうと、読者さんが読んだ時点でそれはウソになってしまうかも知れない。
だから「取材した時点ではこうだった」というニュアンスを含む言葉が必要なのです。
これらの理由があって、私たちは「らしい」「みたい」を使っています。
さらにもう一つ理由があります。
ネットの情報は鵜呑みにせず自分で確かめてほしい、というキモチ
ネットで情報を発信しまくっておいて言うのもなんですが、あらゆる情報は鵜呑みにせず自分で確かめるのがカッコいい、とヒゲ@いーたちは常々思っております。
人の言葉を鵜呑みにするのは人生の主導権を他人に委ねてるようなものだと思うんです。
「本当はヒミツにしたい」や「宇宙一美味しい」など注目を集めるために使われる流行りの言葉にはウソがたっぷり含まれています。「本当に秘密にしたかったら教えないよね」「宇宙中の食べ物食べたことあるの?」とツッコミを入れる姿勢が、自分の人生の主導権を握り続けるために必要、そう考えています。
だからいーたちは言い切ることをせず、敢えて不正確性を残した「らしい」「みたい」という表現を使っています。
いーたち読者のみなさんには、自分で確かめる姿勢を持ち続けていただきたいと思っています。
こんなマニアックな場所まで読んでいただき感謝です。
今後ともいーたちをよろしくお願いいたします。
ヒゲ@いーたち編集長